|
 「きみにあえてよかった」(エリザベス・デール文 フレデリック・ジュース絵 小川仁央訳 評論社) 「きみにあえてよかった」(エリザベス・デール文 フレデリック・ジュース絵 小川仁央訳 評論社)
一月ほど前に子ども用に図書館で借りた絵本。あまり詳しい下読みをせずに借りることが多いので、ペットロス(ペットを失うことによるショック状態)の話だとは知らずに読み始め、子どもにはちょっと悪いことをした。
昨日、図書館へいくのに犬の散歩のコースでもあった公園をとおったのはまずかった。知り合いには会うし、だいたいが公園の中は犬だらけだ。そしてどちらを向いても、そこにいたはずのドンのシルエットが黒く抜けているような気がする。
この道では左側を歩き、この木のところでオシッコ。ここで曲がった…… いくらでも浮かんでくる。べつに公園にかぎらず、近所中がそうなんだけど。
図書館についたら、なんとなくこの本をまた手にとっていた。
それにしても哀しいもんだなぁ……。
犬を飼ったのは初めてではなかったけれど、フルサイズの一生をつきあって、きちんと世話をしたのは初めてだ。室内で一緒に暮らしたのも初めてで、そのくせあんなに愛想のない犬も初めてだった。
深夜、友人とICQ。
彼自身が犬好きでもある友人が気をつかってくれた。あまりこらえようとせずに、思い切り悲しんで弔ってやったほうがいいよと。自分でもそう思う……というか、他にどうしようもない。次の犬っていうのは禁句?っていうから、そんなことないよと答えた。「きみにあえてよかった」も、哀しみから立ち直って次の犬を飼えるようになるまでの話だ。人間の身内が死んだら代わりはないけれど、ペットなら、代わりにはならなくても埋められるものはあるのかもしれない。
ずっと世話をしていた母は体調をくずしているけれど、良くなったら、一度首輪だけ持って全部歩いてくると言っている。散歩したことのあるところ全部。動けなくなってからもきっと行きたかっただろうからと。
一緒にいこうかなぁ、ちょっと心配だし。
|
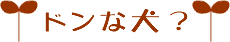

 「きみにあえてよかった」(エリザベス・デール文 フレデリック・ジュース絵 小川仁央訳 評論社)
「きみにあえてよかった」(エリザベス・デール文 フレデリック・ジュース絵 小川仁央訳 評論社)