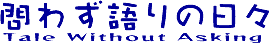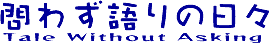『幼稚園の選び方』
▲学校とのあいだで▼
●学力低下という言葉
では話を学校に転じてみよう。
いろいろな問題が指摘されている中で学力低下についての関心は高いと思う。もちろんこれだけ騒がれている学力低下を否定しようとも思わないのだが、しかしどうもわかりにくい部分があるようにも思う。少なくとも低下という言葉を使う以上は、何が何に対してどのように低下したのかということを明確にする必要がありそうだ。
たとえばカリキュラムが簡単または少量化されたことを指して、難しく量の多かったころと比べて結果としての学力が低下したということなら、それはむしろ当然で、低下であっても危機的ではないだろう。学ぶべきものの量が減ったのであれば結果として身に付くものも減るというそれだけのことだ。またあらためて内容を増やすなど、長期的な視点で対応していくしかない。しかしそれとは別に、分数の計算ができない大学生といった話題のように当然身に付けているべき学力が身に付いていないという議論もあるわけで、こちらのほうは学力低下として圧倒的に危機感がある。前者は教えるか教えないか、後者は教えても学ばないという問題で、どうもこういった話題が混同されたまま学力低下という言葉でひとくくりにされていることが多いように感じている。
●ゆとり教育
小学校の場合はさらに「ゆとり教育」という言葉がそこに絡んでくる。2002年度からの学校週五日制の導入が象徴的だが、これはその言葉とは裏腹に、学校での日常生活に「ゆとり」をもたらすものではないようだ。
わかりにくい状況(該当する年齢の子どもがいなければさらにわかりにくいだろう)だが、実際、現場の先生たちにも「ゆとり」の雰囲気は全然なく、むしろカリキュラムをこなそうと必死になっている感じだ。
たとえば上の子は、週五日制が導入された年に入学したが、それまで年二回だった遠足が一回になったときいた。そして一年生当時から居残り付きの宿題に毎日涙して取り組み、勉強なんか大嫌いと口走るようになってそんな経験のまったくなかったわたしたち夫婦を心配させた。あとで知ったことだが、学習指導要領によると二年生までの漢字の割り当ては、わたしたち夫婦のような1960年生まれの人間のそれと比べると151字から240字に増やされていたのだった。約1.6倍である。良し悪しはともかく、このこと自体は少なくとも「ゆとり」とは逆の事態であり、低学年での漢字学習のウエイトを考えるとこの増加の影響は大きいだろう。
要するに現行の「ゆとり教育」はおもに休みが増える分をさしているにすぎず、日常はより窮屈に、詰め込み型になっている面もあるわけだ。
●奇妙な状況
にもかかわらず「ゆとり」という言葉にこだわって、たとえば分数のできない大学生の増加につながるかのような危機感の煽り方をする議論が目立つ気がする。
そういったことから、こんな奇妙な状況にぶつかる。すなわち世間では「ゆとり教育」を引き合いにして学力低下が云々されているが、わが子は自分たちのときよりもよく勉強している(或いは厳しく勉強させられている)という、矛盾を感じさせる状況である。漢字の練習だけでも昔の1.6倍に増えるわけだから、そこに流行りの100マス計算などが加われば昔の子どもの感覚なら拷問かもしれない。そしてその結果としてなお学力低下が懸念されるのであれば、これはもうまったく奇妙としか言いようがないだろう。そして親や教師が、学力低下の懸念や危機感に気おされてさらに勉強を強いれば、その奇妙さやいびつさが助長されていくことになりかねない。
実際のところ、上の子が小学二年生の今、友だちの様子などを見ていてもいわゆるできない子が増えているといったようなことは、わたしは感じない。そしてわたしには上の子はとてもよくやっているように見えていたが、それでも漢字でも九九でもずっと後ろから数番めをキープしていたということで、みんなそんなによくできるのかと率直に感心していたぐらいだった。きけばすでに塾通いをしている子も多いらしく、学力低下?うそー、みんなよく勉強してるよーというのが実感なのである。
●低下しているもの
だが話はそれで終わらない。仮に身近なレベルでの学力低下がそれほど危機的なものでないのであれば、では何も心配は要らないのだろうか。やはり子どもの何らかの能力の低下があるのだろうか。問題はそこなのだ。そしてその何かが低下しているような感じは、わたし自身も妻も持っている。個人的な印象でしかないかもしれないが、それはたとえば妙に幼い感じであったり、現在取り組んでいるものに対する関心の低さであったり、不器用さであったりという形で、子どもと接しているうちに浜辺にうち寄せる波のように伝わってくる。
妻は絵本サークルで読みきかせの活動をしており、すでに二年目が終わろうとしている。そしてその二年間の感想として全体に児童が幼い感じがすると言っている。たとえばどんな本が面白かったかときいても予想よりも低年齢むけの本をあげられたりするらしいのだ。もちろん各人の絵本経験のちがいといったこともあるので一概には言えないだろうが、二年間のトータルな印象だとすればそれなりの意味があるようにも思える。
わたし自身もまた子ども会やPTAを通じて子どもと接する機会がある。子ども会ではソフトボールなどのスポーツ系の活動を見たりしているが、全般に低レベルだ。昨年出場したソフトボール大会でも上位二、三チームがようやく昔のあそびのレベルのような気がした。もちろんそのへんは個人的な印象にすぎないだろう。しかし大会に出るという段になって、どうすれば得点になるか、フライを捕ったらバッターはアウトかといった基本的なルールもよく知らないままでいるというのはどうだろうか。少し問題意識が低すぎないだろうか。あれこれと教えることもできるだろうが、ある程度は自分で解決したり獲得したりしていく力も必要なのではないだろうか。
PTAのイベントでも象徴的なことがあった。学園祭的なイベントで輪ゴムを飛ばす鉄砲を割り箸で作るコーナーの担当に妻がなり、わたしも手伝ったのだが、ほとんどの子どもが割り箸で鉄砲を作ることができなかったのだ。
作るといっても割り箸はあらかじめ切りそろえてあり、あとは輪ゴムで縛っていくだけである。サンプルを見ながらわからないところを教えていくことにしていたのだが、それができない。わたしが直接見た数人は最初からお手上げ状態で「わからん、どうするの」と繰り返すばかり。サンプルを見てもどうすればいいか見当もつかないということだった。結局わたしが最後までを作らねばならなかったのだが、あとからきけば、妻や他のスタッフも一日中ほとんどの割り箸鉄砲を自分で作ったということだった。
結果的にうまく作れないということよりも、その取り組みにあまりにも手応えのないのが気になった。どうなっているんだろうという好奇心もなければ、こうすればいいんじゃないかという思いつきもない。いとも簡単に「そんなん、むずい(難しい)」で終わってしまって、あとは誰か――通常は親や教師だろう――に丸投げしてしまう感じだったのである。そのくせ出来上がったものをよこせとしつこい。
●未熟さか低下か
割り箸を輪ゴムでうまく縛れないといったことは、能力の低下というよりも未熟や未経験と解釈したほうがいいのかもしれない。ソフトボールのルールに無頓着なのも、ルールのあるあそびに対する経験不足という視点でとらえることもできそうだ。だが未熟や未経験であっても、身の回りの状況や課題に対して積極的に取り組めなくなっているのであれば、それ自体が大きな問題だろう。そういう意味でやはり子どもの能力の低下としてとらえていい気がする。
そして学力もまた文字通りの学ぶ力――課題を解決したり知識や知的な技術を獲得したりするための力――だとすれば、割り箸ゴム鉄砲に対する不器用さと同様に、未熟で貧弱な力になっているかもしれないという類推はできてしまう。つまり学ぶ力を含めたもっと大きな範疇の解決能力や獲得能力の低下が子どもに起こっていると考えるほうが現状に合っているような気がするのだ。
●対策されているものといないもの
体力の低下についても、たとえば「人間になれない子どもたち(清川輝基/エイ出版社)」という本には、背筋力が、測定するだけで背筋を痛めてしまう者が出るために公の調査自体が中止されるほどまでに低下しているなどとある。生身の体に関わるだけにもっとも危機的な低下かもしれない。
極端な体力の低下の背後には運動を含むあそびの不足があるはずだというのは素人でも想像がつく。そして極端な体力低下につながるほどあそびが不足しているのなら、あそびを通じて得られるはずの他の能力も低下していると考えるほうが合理的だろう。
あそびを通じて得られる能力――たとえば子どものときのあそびにまつわる熱意や好奇心、執着心、達成感、楽しさといったものが、その後のさまざまな課題に対する解決能力や獲得能力につながっていると感じる大人は多いのではないだろうか。そういった、いわば「あそび力」は当然学力の獲得にも役立ったはずだから、極端な体力低下が起こるほどあそび力が低下すれば、学力低下につながっても当然だと思う。ただ学力は注目度が高いだけにあれこれと対策もされていて、見た目の低下がまだ食い止められているのかもしれない。
日本の教育における「教え過ぎ」を指摘する議論もあるが、現場では指導方法の工夫や反復練習の強化、早期化といった、教えの形で学力の維持や獲得にあたろうとしているケースが多いようだ。
だが、あそびの不足やあそびに対する軽視が子どもの総合的な能力の低下につながっていて、学力低下がその発現の一つにすぎないとしたら、学力だけの対策としての反復練習の強化や早期化などが子どもにとってのよりよい解決策になるのだろうか……。もちろん、あそびを含めた子どもの生活全般を考慮して注意深く行われればいいかもしれないが、安易な形では学力のレベルを維持できてもいわば対症療法にすぎず、子どもの本質的な活力を奪ったりすることにならないだろうか。
実際に子どもの背筋力をどうしようという話はきかないし、あそびの場を提供しようといったこともそれほど積極的には行われていない。教えの形での対応によって結果的に学力の低下がまだ一番よく食い止められていても、その反作用のようにして、体力をはじめとしたあそびを通して得られる力全般の低下にさらに歯止めがかからなくなっている可能性はないだろうか。
●就学前のあそび環境
では都市を改造して、子どもが自由にあそべる広場を作ろう、犯罪者を排除すべく徹底的な対策もしようと言ったところでそんなことはいつになるかわからない。子どもが成長を止めて待っててくれるようなこともない。だからこそ、身近にできる最初の重要な対策として、就学前にできるだけしっかりあそばせるのがよいと考えるのである。そしてそれが可能なのは幼稚園だということになる。
自分の記憶をたどってみると、十歳ぐらいまでが友だちと頻繁に外を走り回ってあそんでいた時代だった。ということは、就学前であそびの時代の五、六割がすでに終わってしまうことになる。しかもあそび環境の悪化から、幼稚園での生活がその年齢の子どものあそびの質そのものをコントロールしてしまうところもある。ということは幼稚園時代をしっかり過ごせればあそびの時代全体に対する影響を現実的に一番小さくできるかもしれないが、逆にその間のあそびを幼稚園が軽視してしまうと子どものあそび体験そのものが極端に小さく貧弱なものになってしまう可能性がある。そしてあそびを通して身に付くはずの力も同様に小さく貧弱なものになってしまうかもしれない。それが人生における最初の損失だとしたら、その損失を現状の小学校での最初の四年間で取り返すことは簡単ではないだろう。やる気のない中学生や高校生といった現象は、小さいときからそのようにしてあそびを奪われ、あきらめてしまった――いや、あきらめさせられてしまった子どもの、なるべくしてなった姿のようにも思える。
▲はじめに▼
▲子どもを取り巻く状況▼
▲学校とのあいだで▼(このファイル)
▲入園と転園▼
▲おわりに▼
HOME・ご案内・アメとムチの日々・あるばむ・暖談畑・おまけ・Exit & Links