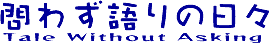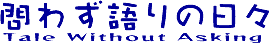『幼稚園の選び方』
▲入園と転園▼
●二つの立場
幼稚園では、小学校に対してまず大きく二つの考え方があると思う。
一つは、小学校での授業に耐えられるような、または授業に役立つような学力や忍耐力の養成を目指す立場で、いわば小学校の予備校的な存在になろうとする考え方だ。
それに対してもう一つは、あそびを中心とした学力以前の子どもらしい活力を支えることで、小学校を含めたその後の生活に対する基礎を築こうとする立場である。
もちろんそれらの中庸もあり、必ずしもきれいに分類できるわけでもないだろうが、考え方としての両者のちがいは大きい。
たまたまだが、上の子は前者の幼稚園から後者の幼稚園に転園した、とわたしは考えている。大阪市に固有のことかもしれないがどちらも私立の幼稚園だ。公立の幼稚園は少なく、区内でいえば10以上ある幼稚園のうちの2つだけで、いずれもわが家からは遠くて通えない。現実に私立幼稚園しか選択肢がない、そういう状況での話だ。そして実際に転園前の幼稚園では「月々の行事をがんばってこなしていくことが小学校での生活を円滑にする訓練になる」ということをそういう表現で言われた。
●入園前にはわからなかったこと
入園前のわたしたち夫婦の幼稚園の選択に対する考え方は、厳しすぎたり自由すぎたりしないごく普通の教育方針のところ、しっかりあそべるようになるべく広い園庭のあるところ、下の子の出産を控えていたのでいざというときのためにバス通園の可能なところという程度だった。妻が自宅から遠くない5つの幼稚園に見学にゆき、最初に入園させた幼稚園を選んだのだが、ということは、わたしたちには先に述べた小学校の予備校な存在であろうとするような幼稚園の考え方――行事を小学校生活の訓練と認識しているような考え方――はその時点では見えなかったわけである。
見えない人は多いのではないかと思う。特にわたしは、これだけあそび環境が悪化している中で幼稚園が子どものあそびの機会をさらに奪うような発想をするとはまったく想像していなかった。たぶんわたし自身が幼稚園時代を何の問題もなく通過したために問題意識そのものがなかったせいもあるだろう。
実際に、最初の幼稚園では絶え間なく行事が設定され、その練習をすることが幼稚園での生活になっていた。たとえば五月には母の日の参観、六月には父の日の参観、七月は七夕音楽会に夏祭り、九月は十月初めの運動会の練習、十一月には制作展、十二月音楽発表会、一月マラソン大会、二月劇の発表会といった具合である。そのすべてで演技や遊技や競技があって本番に向けて練習を重ねるのが園児の生活になっていたわけだ。そしてこれらのあいだを埋めるようにお芋掘りやぶどう狩り、おもちつき、遠足、宿泊保育などがある。
そういったことは大なり小なりどこの園でもあるものだが、やはり程度問題だろう。音楽会などのために早朝練習をすると言われたときはさすがに驚いたものだった。もちろん対応できる子どももいるだろう。そしてストレスが大きくても、一旦解放されれば思い切りあそべるような環境があればまたちがうのかもしれない。だが現状ではすでに述べたように、幼稚園が行事の練習に終始してしまうと子どもにはもう満足にあそぶところがなくなってしまうのだった。
そんな事態になるとは入園前にはまったく予測できなかった。あとできいた話だと、園庭の見えるマンションに住んでいる人には、園児が自由にあそんでいるのを見たことがないと言い切る人さえいるとのことだった。
余談になるかもしれないが、行事の連続は園児だけでなく保育師も相当に忙しいだろう。制作展の前など夜になっても教室に灯りのともっている日がつづいたり、音楽会などで早朝練習があったりすれば勤務時間も長くなるだろう。保育師が体力のある若い人ばかりなのも頷ける気がしたものだった。しかしいくら体力があっても、余裕がなければ大勢の子どもたちに細かい神経を配ることはできない。子どもが早朝練習でよれよれになっている旨を伝えたとき「本番が近くてわたし自身が必死になってて気がつきませんでした。すみません」とあっさり言われて唖然としたものだった。「もう少しなのでお家でも、がんばろうねって励ましてあげてください」とも言われたが、保育師が自分の仕事をがんばることと混同されているような気がした。
●転園
もともと、家を出るときの「いってきます」の声に元気がないことは気になっていた。入園した当初からで、通園に慣れても一向に元気がこもらなかった。やがて休みたいという日がぽつぽつとあらわれ、それが特定の曜日に集中するようになる。ストレスの強い日は帰宅後の様子も荒れ気味で、それは見ているとわかった。秋ごろにははっきりと幼稚園に行きたくないという日が増えはじめ、そのあたりで親も転園を考えるようになり、年が明けてから転園を実行したのだった。
そういう状況なので特に追いつめられていたわけではない。たしかに子どもは不満を感じていたようだが、どちらかといえば親の、子どもをのびのびあそばせてやりたいという考え方による転園だった。
だが実際には精神的に追いつめられてしまう親御さんもおられるようだ。子どもが園に馴染めないということで相談にいき、お宅のお子さんに問題があるためだと言われたりするケースも現実にあるらしい。核家族でなにかと苦労しながら子育てをしている若い母親などが幼稚園からそのように言われたときのダメージは想像に余りあるが、こういったことは単純に方針のちがいだと理解するべきだろう。子どもの能力や資質に結びつけてしまうと苦しいだけだと思う。わが家の場合も、幼稚園側は希なケースとして特に問題にも感じなかったようだった。特定の曜日に園児の休みが集中していてもわからないか、気にならないということでもある。そして希扱いされるのもなんなので付記すると、近所で同じ園に通う子どもの親にちょっときいただけでも、毎朝行きたがらないという話はゴロゴロ出てきたのだった。転園にはやはり多少のエネルギーは要るわけで、二年保育であればもう一年の辛抱だとそのまま通わせるケースも多いのかもしれない。
しかし結果的に転園はしたものの、最初の幼稚園が特殊だとはやはり思えない。そういう評判もない。言い換えると、その教育方針は近辺の私立幼稚園の平均的な範疇であるということなのだろう。実際に体験すると各園でいろいろと違いはあるかもしれないが、あそびという観点では、たっぷりとあそんで育つ活力のある子どもが減っていく(少なくとも増えることはない)システムがすでに出来あがってしまっているようにも見える。
●風邪の頻度
転園先の幼稚園は、子どもをのびのびあそばせてくれるところだったが、付け加えたいことがもう少しある。
まず一つは、風邪ひきなどの疾患についてだ。これはうちの子の場合、転園前後で劇的に少なくなった。転園前はほんとうによく風邪をひき、当時0歳の下の子にもよくうつした。二人とも咳をすると吐いてしまうので夜中に飛び起きる日がつづくことにもなり、結果的に家族の全員がよく風邪をひいた厳しい一年だった。誰かが風邪をひいている状態が三ヶ月つづいたこともあり、かなり暗い気分になった時期もあった。
それが転園を境に激減した。風邪をひいたかなと思ってもひきこまずにおさまってしまうので感覚的には0になった感じでさえある。これも幼稚園でそれほどの違いがあるなどとは想像もしていなかったのだが、考えてみれば教室の広さや換気の状態、一クラスの人数、運動の量といった条件によって風邪ひきの率もちがっていて当たり前だろう。月に一回風邪をひいて一週間ほどおとなしくしているとしたら、それだけで子どもの活動量は25%ほど減ってしまうことになる。小さな数字ではないはずで、可能であれば風邪ひきの少ないところで生活させてやりたいものだ。
●小学校への対応
もう一点、あそびを重視するような方針だと、いわゆる小一問題のような学校での授業に対応できない子どもになってしまうという考え方もあるかもしれない。だがこれは考える順番がちがっている。まず小学校が、それまで幼稚園児だった子どもが慣れるための時間をとらなければならないのであって、入学した時点で子どもが座って授業を受けることに耐えられる状態になっている必要はないはずである。入学時に必要があるのは学校という集団生活の場に所属する意識で、これは幼稚園での生活を自発的に楽しんだほうが形成されやすい。
……などと素人が断じても説得力がないのだが、たとえばこういうシーンを転園先の幼稚園で経験した。それまでは園庭に集合、整列するときにトントンマエというのをやらされていたのだが、それがなく全員が静かに、半ば自発的にだいたいの列についたのである。トントンマエというのは整列のときの「前にならえ」を子ども用にリズミカルにしたもので、採用している幼稚園も多いらしい。だが小学校が集団生活である以上、それがないと整列できないのと、なくてもできるのとどちらが適しているかは明らかだろう。
小一問題ではむしろあいさつや食生活など基本的な生活習慣の不全とともに指摘されることも多いようだ。あそびを重視することはしつけや生活習慣の習得とは別の次元の話だし、自由にあそぶということも、何をやってもいいということとは全然ちがう。そのあたりは実際に園児を見てどういう教育がされているかを判断すればいいと思うが、とりあえずは基本的な生活習慣に対しては第一に親がその責任を負うべきだろう。
▲はじめに▼
▲子どもを取り巻く状況▼
▲学校とのあいだで▼
▲入園と転園▼(このファイル)
▲おわりに▼
HOME・ご案内・アメとムチの日々・あるばむ・暖談畑・おまけ・Exit & Links