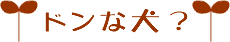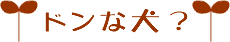|
2000年5月13日(土)
何も食べなくなってからすでに十日になる。痩せこけて、頭蓋骨の輪郭もくっきりと浮き上がっている。もう満足に歩くことさえできない。そのくせ目の輝きだけはあまり変わらず、食べさえすればすぐに元気になりそうなのに、何も食べずに水ばかり飲んで一日中じっとしている。このまま衰弱死するのを待つつもりなのだろうか? がんばってくれよ、まるで自殺じゃないかよ……。
めぐり合わせも悪かった。今年の正月休みに、溜まった膿で顔の形が変わるほど左耳の外耳炎を悪化させてしまった。すでに両耳とも聞こえなくなっているが、今年たぶん十五年め――人間でいえばおよそ八十歳らしい――をむかえる老犬にはきびしい試練だったろう。
さらに同じことが三月末にも起こった。そのときも運が悪く、獣医先生はたまたまのお休み。代わりにかかった医者は結果的に楽観的すぎたようで、またもや顔の左半分が腫れ上がってしまった。このときは膨れ上がった皮膚が自然に傷ついて膿が流れ出すのを待ったため、実際についた傷はこめかみのあたりから頬までを大きく裂いた。そんな大きな傷に不慣れなため気が気ではなかったが、治ってみれば毛があるせいか人間の場合ほど傷跡は目立たなかった。その後は左耳が悪化することはなかった。
ゴールデンウイークごろから今度は右耳のほうが腫れだした。暦どおりではあるけれど、やはり休みが絡む。五月の四日、わたし自身が風邪による高熱に襲われた日、ドンもぼんやりとしてまともに歩かなくなってしまった。その時点での腫れは大したことがなく、突然ひどく弱ったような印象が強かったために、わたしの母は急死を心配して寝つけなかったらしい。
六日、左耳のときのように、形相が変わるほど腫れ上がる。今回は後頭部のほうにかけても腫れが広がっているようだった。見ているのもつらいので切開して膿を出してやってくれと、母が医者に頼んだ。たしかにこめかみのあたりで皮膚が薄くなっており、ほっておいてもそこから破れそうだった。あまり乗り気ではないようだったものの、医者は切開してくれた。コップに一杯ぐらいの膿が出て、腫れは小さくなった。しかし傷の位置が高く、それより下に溜まっているものは出にくい。また麻酔も無しでメスでつけた傷などすぐにふさがるので、せいぜい膿出ししてやってくれとのことだった。母は懸命にそのとおりにしていた。この日、医院の外で順番を待っているときに、初めて血の塊のような便をした。
八日、前回までなら食欲も出てきて元気も回復してくる段階のはずだった。しかし今回はそんな兆候はない。それよりも腫れが戻りそうな具合だった。なにも食べようとせず、血の塊のような便の頻度が増えて、衰弱が進むばかり。予防もし、治療もしているのに結局進行してしまった症状といい、その後の回復といい、全体的な体力や抵抗力がかなり落ちている。やはり年齢によるものも大きいのだろう。
十日、医者で便のことを言うと、耳のほうの化膿を抑えるために殺菌力を優先した注射をせねばならなかった、そのため腸内細菌まで影響を受けているのかもしれないとのこと。抗生物質の種類を変えた注射を打った。切開したところが塞がったために腫れも戻っている。しかし同じところを切開しても同じ結果になるだけなので、今度は自然に破れるのを待つしかないようだった。こめかみから頬にかけても腫れているが、さらに後ろの、首から肩にかけての腫れも固く大きくなっていた。
十一日、夜の散歩(といってもほんの少し歩くだけ)に連れて出た母がすぐに帰ってきた。腫れが破れたらしく、ポトポト落ちる膿をなめて動かないから引き返してきたとのこと。待ちかねていた、頬の下のほうの傷だった。これで楽になるかもしれないと、タオルとティッシュペーパーとで必死に膿を取る。そのうちに首のうしろのほうもどこかで破れたらしく、抱きかかえていたわたしのTシャツが濡れていた。これで治る、これで治るぞと繰り返しながら、母と二人で必死になって膿を取った。いろんなところで力が入っていたかもしれない。ドンも大変だっただろう。それでなくとも衰弱しているので、一段落すると腰が抜けたようになって、玄関の段の上から土間(土ではないが)にヘナヘナと落ちてしまった。抱き上げて寝かせてやる。
腫れが無くなると、痩せている体が浮かび上がる。それでも、これでよくなるだろうという期待のせいでほっとするものがあった。
十二日、腫れはなくなったが、相変わらず何も食べようとしない。医者ではやはり化膿止めの注射。栄養剤の点滴でもおこなったほうがいいのではないかという気がするが、化膿を抑えて、耳のほうが落ち着けば食べるだろうとのこと。
……だが、その後も結局なにも食べない。
実はわたしはわりと楽観していた。だいたいが元々は外耳炎なのだ。化膿が進んで悪化したとしても、放置しているわけではないのだから致命的なことにはならないだろうと推測していた。それに、いくら食べないといっても水さえ飲んでいれば一週間や十日の絶食で命を落とすということもないだろう。その間に食べられるように回復しさえすれば、少々痩せていてもすぐに元気になるはずだ、とそんなふうにも考えていた。個体年齢をドンと争って、おそらく最近抜かされたであろう母も、概ねそんなふうじゃなかったかと想像している。
だが、良くなる兆しがない。そして衰弱が進む一方だ。
「とにかく歳やから……」という母の諦観が痛々しい。
ほんとうか? ほんとうに、彼の最期が近いのだろうか。
医者とのコミュニケーションがうまくいってないだけではないのだろうか。二、三日に一回診てもらう時点では、それぞれ、そのときの症状に合わせた処置をして少し様子をみる、ということで理解はしているつもりだ。ただ、老化を含めた全体的な流れの中でその時その時がどういう段階や状態にあるかという位置づけは、こちらではわからない。せいぜい想像や推測ができるだけだ。それに対して医者のほうは常にそういう視点が頭にはいっているのだろう。医者の目で見れば典型的な進行であるのに対して、こちらにとっては初体験の展開でしかも衰弱が進むばかり、という状況ではないのだろうか。
衰弱しているのなら栄養剤の点滴は? しかし、それがいたずらな延命につながるだけなのであれば……そんなこともわからない自分がもどかしい。もし彼が人間であれば、まず入院、そして検査という手順が当然のように進むのだろう。そういうふうにすれば元気になるのだろうか。元気にならずとももう少しましになって、歩いて、散歩できるようになって、もう数ヶ月か、あるいは半年なり一年なりを過ごすのだろうか。それが彼にとってつらいことになる可能性はないのだろうか。
同じことを、母も自問しているだろう。否応なく自分のことも重ね合わせて、そして「とにかく歳やから」と言うのだろう。「あれこれしてもなぁ、しんどい思いさせるだけかもしれへんし……」と言うのだろう。「寿命があるんやったら元気になるのに、自分で食べへんのやから」と。
食べ始めさえすればすぐに元気になると信じていたのだけれど、今日、立とうとして立てなかった姿を見て自信が無くなってしまった。このまま食べられずに衰弱していくのだろうか。それとも病気のストレスが老衰を著しく加速したということなのだろうか。そして生きようとする気力が失せたのか?
くそっ、がんばれよ! がんばってくれよ! 母のためにもがんばってくれよ!
2000年5月14日(日)
とうとう寝たきり状態になってしまった。母はもうあきらめている……というより、自身も疲れていて風邪ぎみのようだ。夜も眠れないのだろう。どうすることもできない自分の無力感がたまらない。
2000年5月15日(月)
獣医につれていく。栄養剤500mlの点滴。体重が三十キロないことを考えれば相当な量なのだろう。やはり医者にすれば、前回以降症状が改善していれば食べるようになって回復にむかうだろうし、そうでなければ点滴ということのようだ。ただあいだに土日が入ったのが不運だったということか……。そのへん、言っておいてくれれば休日でもやっているところを探すなどするのにとは思うが、それはこちらが判断するべきことなのかもしれない。
目がしっかりしているのでなんとか回復にむかうのではないかとのこと。一日ほどすれば立てるようになるのではないかとは思うが、それよりも問題はそれ以後食べようという気がおこるかどうかだ、という。まずは砂糖水から飲ませるのがいいらしい。
|